日本では、難聴者を取り巻く環境が決して良いとはいえない。これは、健聴者の難聴についての理解度が高くないことが関係している。どんな不便があるのか、どのようなサポートを求めているのか。目に見えない障がいであるが故に、その実際を知るのは容易ではない。
最近、難聴を理解するための手段として、注目を集めているのが“バーチャルリアリティ(VR)”だ。補聴器のリーディングカンパニーであるオーティコン補聴器は、東京・渋谷で開催された「2020 渋谷。超福祉の日常を体験しよう展(超福祉展)」で、難聴と先進補聴器の世界を体験できるVRソリューションを展示した。

東京・渋谷で開催された「2020 渋谷。超福祉の日常を体験しよう展(超福祉展)」
超福祉展は、障がい者をはじめとするマイノリティや福祉に対する心のバリアを取り除くことを目的としたイベントで、2014年から毎年開催され、今年で6回目を迎える。会期は9月3日~9日の1週間で、イノベーションを期待させる福祉機器やテクノロジーが展示されたほか、有識者によるシンポジウムなども行われた。
9月5日には、オーティコン補聴器の木下聡プレジデントとDeaf VRの開発者であるCNSの牧村正嗣プロデューサーによる対談があり、ソリューション開発の経緯から日本の小児難聴を取り巻く状況と課題まで、幅広いテーマについて議論が交わされた。
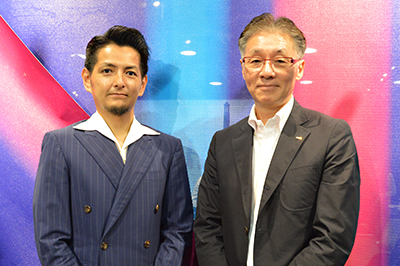
左からDeaf VRの開発者であるCNSの牧村正嗣プロデューサー、
オーティコン補聴器の木下聡プレジデント
牧村氏がDeaf VR開発を考えたきっかけは、小児難聴のお子さんだったそうだ。難聴を理解するためにろう学校で難聴体験会に参加した牧村氏だったが、その再現性の低さに衝撃を受けたという。「耳栓やイヤーマフで耳穴を防ぐのだが、音は体の振動などを通して伝わってくるので、実際の難聴を体験できているとは言い難かった」(牧村氏)。

難聴のお子さんがDeaf VR開発のきっかけになったという牧村氏
そこで、自身の映像制作者としての知見を生かしてつくり上げたのが、映像と音を組み合わせることで「聞こえない・聞こえにくい世界」を体験できるDeaf VRだった。現在、「道路編」「カフェ編」「食卓編」などのコンテンツがあり、それぞれのシーンで難聴者が経験する疎外感や不自由さを再現している。
たとえば、「道路編」では「音声情報がないとはどんな感覚なのか」を体験することができる。健聴だと勘違いしがちだが、音量の大きいクラクションであっても難聴者が聞き取りにくい周波数の音であれば耳に入ってこない。音の方角などを認識しづらいため、危険を検知することが非常に難しい。
カフェであれば、会話している相手の声だけでなく、人の歩く音や店内の他の会話など、さまざまな音が溢れているという点がポイントだ。健聴者であれば、聞きたい音を無意識に選択できるが、難聴者は音の取捨選択をすることが難しい。不要な音が次から次へと飛び込んでくる状況は、実はとても大きなストレスになるのだ。
牧村氏とオーティコンが接点を持ったのは、どちらもVRによって難聴者の聞こえの状態や聞き取りにくさを健聴者が疑似体験できる機会をつくる、というアプローチを試みていたからだ。オーティコンは2016年に発売され、補聴器業界にパラダイムシフトを起こした「オーティコン オープン」が実現する聞こえの世界をVRで再現している。
ユーザーの正面の音声のみを届ける指向性機能を使った従来の補聴器の聞こえから、騒がしい環境下でも、全方位からの音声を必要な会話はそのままに、不要なノイズのみを抑制してバランスの取れた自然な音を耳に届ける「オーティコン オープン」の聞こえがどれだけ進化しているのかを伝える手段としてVRを活用してきた。

超福祉展には「オーティコン オープン」が実現する聞こえの世界を
VRで体験できるコーナーも用意されていた
“健聴者に難聴を伝える”ことを重要視するのは、難聴が決して他人事ではないからだ。牧村氏のようにお子さんが生まれながらに難聴を持っているということは、決して珍しくない。新生児の段階で難聴の有無を早期発見するスクリーニングシステムはあるが、木下プレジデントによると、日本での検査実施率は80%程度で幼少期になってようやく発覚するケースも少なくないという。東京都でも今年4月から一部助成が始まるなど徐々に浸透しつつあるが、制度としてもまだまだ課題が残っている。
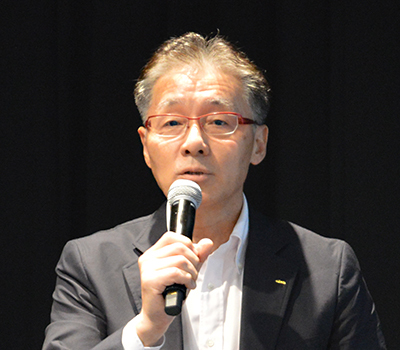
なぜ健聴者に難聴を伝えることが必要なのか説明する木下プレジデント
牧村氏は、新生児聴覚スクリーニングを「すべての新生児に義務化すべきだ」と主張する。牧村氏のお子さんはスクリーニングによって早期に難聴が発覚し、すぐに補聴器を用いて音を耳に入れる訓練を行うことができた。その経験から、「言語中枢ができていない時期に音を入れるのと入れないのでは大違い」だということを理解している。

木下プレジデントと牧村氏の対談には多くの来場者が集まった
「いずれはハンディキャップを補うのではなく、健常者以上の力を身に着けることができる。補聴器がそんな存在になれば」。木下プレジデントがそう語るのは、夢物語ではない。補聴器のレベルは現時点で、そのビジョンに近いところまできている。超福祉展のイベント名にも含まれている“2020年”も目前だ。人がテクノロジーに遅れをとらないためにも、一人ひとりの意識を変革すべきタイミングにきているだろう。(BCN・大蔵 大輔)
最近、難聴を理解するための手段として、注目を集めているのが“バーチャルリアリティ(VR)”だ。補聴器のリーディングカンパニーであるオーティコン補聴器は、東京・渋谷で開催された「2020 渋谷。超福祉の日常を体験しよう展(超福祉展)」で、難聴と先進補聴器の世界を体験できるVRソリューションを展示した。

超福祉展は、障がい者をはじめとするマイノリティや福祉に対する心のバリアを取り除くことを目的としたイベントで、2014年から毎年開催され、今年で6回目を迎える。会期は9月3日~9日の1週間で、イノベーションを期待させる福祉機器やテクノロジーが展示されたほか、有識者によるシンポジウムなども行われた。
9月5日には、オーティコン補聴器の木下聡プレジデントとDeaf VRの開発者であるCNSの牧村正嗣プロデューサーによる対談があり、ソリューション開発の経緯から日本の小児難聴を取り巻く状況と課題まで、幅広いテーマについて議論が交わされた。
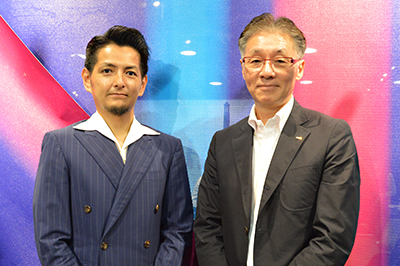
オーティコン補聴器の木下聡プレジデント
牧村氏がDeaf VR開発を考えたきっかけは、小児難聴のお子さんだったそうだ。難聴を理解するためにろう学校で難聴体験会に参加した牧村氏だったが、その再現性の低さに衝撃を受けたという。「耳栓やイヤーマフで耳穴を防ぐのだが、音は体の振動などを通して伝わってくるので、実際の難聴を体験できているとは言い難かった」(牧村氏)。

そこで、自身の映像制作者としての知見を生かしてつくり上げたのが、映像と音を組み合わせることで「聞こえない・聞こえにくい世界」を体験できるDeaf VRだった。現在、「道路編」「カフェ編」「食卓編」などのコンテンツがあり、それぞれのシーンで難聴者が経験する疎外感や不自由さを再現している。
たとえば、「道路編」では「音声情報がないとはどんな感覚なのか」を体験することができる。健聴だと勘違いしがちだが、音量の大きいクラクションであっても難聴者が聞き取りにくい周波数の音であれば耳に入ってこない。音の方角などを認識しづらいため、危険を検知することが非常に難しい。
カフェであれば、会話している相手の声だけでなく、人の歩く音や店内の他の会話など、さまざまな音が溢れているという点がポイントだ。健聴者であれば、聞きたい音を無意識に選択できるが、難聴者は音の取捨選択をすることが難しい。不要な音が次から次へと飛び込んでくる状況は、実はとても大きなストレスになるのだ。
牧村氏とオーティコンが接点を持ったのは、どちらもVRによって難聴者の聞こえの状態や聞き取りにくさを健聴者が疑似体験できる機会をつくる、というアプローチを試みていたからだ。オーティコンは2016年に発売され、補聴器業界にパラダイムシフトを起こした「オーティコン オープン」が実現する聞こえの世界をVRで再現している。
ユーザーの正面の音声のみを届ける指向性機能を使った従来の補聴器の聞こえから、騒がしい環境下でも、全方位からの音声を必要な会話はそのままに、不要なノイズのみを抑制してバランスの取れた自然な音を耳に届ける「オーティコン オープン」の聞こえがどれだけ進化しているのかを伝える手段としてVRを活用してきた。

VRで体験できるコーナーも用意されていた
“健聴者に難聴を伝える”ことを重要視するのは、難聴が決して他人事ではないからだ。牧村氏のようにお子さんが生まれながらに難聴を持っているということは、決して珍しくない。新生児の段階で難聴の有無を早期発見するスクリーニングシステムはあるが、木下プレジデントによると、日本での検査実施率は80%程度で幼少期になってようやく発覚するケースも少なくないという。東京都でも今年4月から一部助成が始まるなど徐々に浸透しつつあるが、制度としてもまだまだ課題が残っている。
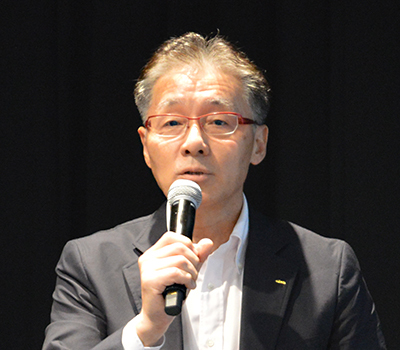
牧村氏は、新生児聴覚スクリーニングを「すべての新生児に義務化すべきだ」と主張する。牧村氏のお子さんはスクリーニングによって早期に難聴が発覚し、すぐに補聴器を用いて音を耳に入れる訓練を行うことができた。その経験から、「言語中枢ができていない時期に音を入れるのと入れないのでは大違い」だということを理解している。

「いずれはハンディキャップを補うのではなく、健常者以上の力を身に着けることができる。補聴器がそんな存在になれば」。木下プレジデントがそう語るのは、夢物語ではない。補聴器のレベルは現時点で、そのビジョンに近いところまできている。超福祉展のイベント名にも含まれている“2020年”も目前だ。人がテクノロジーに遅れをとらないためにも、一人ひとりの意識を変革すべきタイミングにきているだろう。(BCN・大蔵 大輔)






