【外食業界のリアル・4】 外食業界はコロナが明けて、インバウンドの後押しもあって急速な需要の高まりを見せ、深刻な人手不足の時代へと突入した。アルバイトの外食離れもあって、貴重な人材は各店舗が取り合う形となり、時給はもちろんのこと、採用の獲得単価も高騰を続けている。そんな中、不平不満をいうことなく安い価格で電話を取ってくれるAIコールは急激に拡大している。今回はAIコールの実情とこれからについて解説したい。
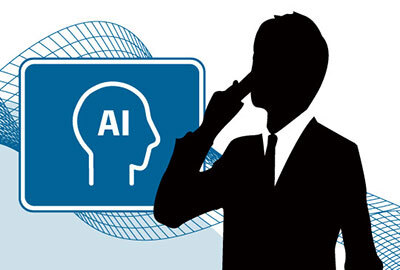
だが、人手不足が深刻になった今、店長が全ての電話を取って席を調整する余裕がなくなった。また経験が浅いうちに店長になる人も増えてきており、100点を目指すのではなく70点を超えるオペレーションが求められる傾向が強くなってきた。
そんな中でAIの技術が進化し、一定ラインをクリアすることができるようになったことで、AIコールが普及してきたわけである。
回答に応じて、AIで受けるものや店舗で対応するもの、SMSでフォームを送って選択してもらうなどとリアクションが変わってくるわけだ。もちろんお店によって何を店舗で対応するのかは変わってくるので、個別に分岐を変えていく形となる。設計がきちんとしていれば、概ねの電話には一定水準以上の対応することが可能となる。
次にAIコールでできないことはなにかを考えてみる。
現時点では「コース予約」を取るのは難しい。音声として認識することは出来るが、似たようなコース名が多かったり、内容が同じでも掲載している媒体によって名前が異なっていたりなど、短いスパンで変わっていくものを正確に運用していくことが実質できない。また、柔軟な調整作業も難しい。例えば、「30人で予約するので一品料理を追加して欲しい」「サプライズでケーキを出したいので冷蔵庫で保管しておいてもらうことは可能か」などの要望に対応できない。
つまりAIといえども、事前に設計されたものに対してでしか回答することができない(正確には店側がしたくない)のである。
「導入後、店舗にかかってくる電話が劇的に削減されて助かった」という声はよく聞くが、詳細に分析をしていくと決して楽観視できない状態となっているケースもある。店舗への電話が減った分そのまま予約件数・予約制約率が大幅に落ちており、売り上げ減少になっていたりする。また、顧客がAIコールの分岐を繰り返した上で結局、店舗に電話が転送されてしまっているが、その電話が取れていないことで、店への不安・不信の要因になっていることもある。
AIコールを導入することはゴールではない。何のために導入するのか、何を委ねて何を委ねないのかをしっかりと設計しないと成果にはつながりにくい。
現状はまだまだ課題のあるAIコールであるが、凄まじい勢いで進化しているのも事実である。今ある課題も近いうちに解消されていく可能性は高い。導入店舗が増えてくれば、顧客もAIコール自体にも慣れてきて、当たり前のようになってくることも近い将来なるかもしれない。もちろんAIコールが当たり前になった際、“人が対応する”だけで付加価値となるということも同時に起きる。
優秀な店長が電話で何をどのように調整しているのか。そのデータが蓄積されていくと、そのノウハウが"見える化"されていく。そうするとAIコールはそのうち店長の教えをしっかりと受け継いだ優秀な「副店長」となるだろう。それはもう目の前まで来ている。(イデア・レコード・左川裕規)

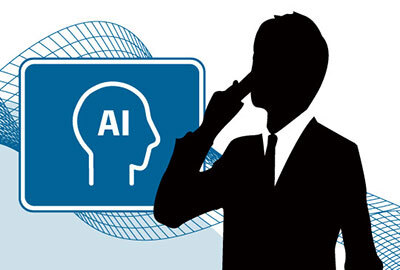
外食業界でAIコールが増えている背景
外食業界では売り上げの生命線である予約電話を重要視し、店舗で然るべくメンバーが対応すべしという考えが根強くあった。顧客の要望をしっかりとヒアリングした上で、効率の良い時間帯に最適な席へ案内する。予約が増えてくると、すでに入っている予約の席を調整して、パズルのようにタイムテーブルを埋めていく。店舗のレイアウトや時期による予約の入り方など、勘と経験をもとにした配席技術が確かにそこにはあった。だが、人手不足が深刻になった今、店長が全ての電話を取って席を調整する余裕がなくなった。また経験が浅いうちに店長になる人も増えてきており、100点を目指すのではなく70点を超えるオペレーションが求められる傾向が強くなってきた。
そんな中でAIの技術が進化し、一定ラインをクリアすることができるようになったことで、AIコールが普及してきたわけである。
AIコールでできること・できないこと
AIコールは全ての質問に対して、都度考えて回答しているわけではない。分岐を繰り返しながら、あらかじめ用意された回答をする形となっており、以前から存在するIVR(自動音声応答システム)と基本的なベースの仕様は同じと思ってもらっても良い。よくあるパターンでは、最初に「新規の予約」「登録済み予約の変更」「その他問い合わせ」なのかを聞き、「新規の予約」であれば次に「当日予約」「明日以降の予約」なのかを聞くという風に進んでいく。回答に応じて、AIで受けるものや店舗で対応するもの、SMSでフォームを送って選択してもらうなどとリアクションが変わってくるわけだ。もちろんお店によって何を店舗で対応するのかは変わってくるので、個別に分岐を変えていく形となる。設計がきちんとしていれば、概ねの電話には一定水準以上の対応することが可能となる。
次にAIコールでできないことはなにかを考えてみる。
現時点では「コース予約」を取るのは難しい。音声として認識することは出来るが、似たようなコース名が多かったり、内容が同じでも掲載している媒体によって名前が異なっていたりなど、短いスパンで変わっていくものを正確に運用していくことが実質できない。また、柔軟な調整作業も難しい。例えば、「30人で予約するので一品料理を追加して欲しい」「サプライズでケーキを出したいので冷蔵庫で保管しておいてもらうことは可能か」などの要望に対応できない。
つまりAIといえども、事前に設計されたものに対してでしか回答することができない(正確には店側がしたくない)のである。
AIコール導入店舗の実情と今後について
それでも人手不足の中でAIコールを導入することのメリットは非常に大きい。が、落とし穴も忘れてはならない。「導入後、店舗にかかってくる電話が劇的に削減されて助かった」という声はよく聞くが、詳細に分析をしていくと決して楽観視できない状態となっているケースもある。店舗への電話が減った分そのまま予約件数・予約制約率が大幅に落ちており、売り上げ減少になっていたりする。また、顧客がAIコールの分岐を繰り返した上で結局、店舗に電話が転送されてしまっているが、その電話が取れていないことで、店への不安・不信の要因になっていることもある。
AIコールを導入することはゴールではない。何のために導入するのか、何を委ねて何を委ねないのかをしっかりと設計しないと成果にはつながりにくい。
現状はまだまだ課題のあるAIコールであるが、凄まじい勢いで進化しているのも事実である。今ある課題も近いうちに解消されていく可能性は高い。導入店舗が増えてくれば、顧客もAIコール自体にも慣れてきて、当たり前のようになってくることも近い将来なるかもしれない。もちろんAIコールが当たり前になった際、“人が対応する”だけで付加価値となるということも同時に起きる。
優秀な店長が電話で何をどのように調整しているのか。そのデータが蓄積されていくと、そのノウハウが"見える化"されていく。そうするとAIコールはそのうち店長の教えをしっかりと受け継いだ優秀な「副店長」となるだろう。それはもう目の前まで来ている。(イデア・レコード・左川裕規)









