ものづくりの伝統を守りながらベンチャーであり続ける――第168回(下)

森澤 彰彦
モリサワ 代表取締役社長
構成・文/小林茂樹
撮影/長谷川博一
週刊BCN 2016年09月19日号 vol.1645掲載
モリサワの創業者である森澤信夫氏は、東洋一の規模といわれた星製薬の印刷部で働いているとき、「写真で字を組む機械」が英国で研究されていると聞き、強い関心を抱いたという。100年ほど前のこと、活字を組んで薬の効能書きを印刷していた信夫氏は、その研究に没頭。試作機をつくるやいなや、2年足らずで同社を辞めて事業化に踏み切る。おそらく、そのスピードと集中力は尋常なものではなかったはずだ。そうした起業家精神が受け継がれてきたからこそ、同社はトップランナーであり続けられるのだろう。(本紙主幹・奥田喜久男)


心に響く人生の匠たち
「千人回峰」というタイトルは、比叡山の峰々を千日かけて駆け巡り、悟りを開く天台宗の荒行「千日回峰」から拝借したものです。千人の方々とお会いして、その哲学・行動の深淵に触れたいと願い、この連載を続けています。
「人ありて我あり」は、私の座右の銘です。人は夢と希望がある限り、前に進むことができると考えています。中学生の頃から私を捕らえて放さないテーマ「人とはなんぞや」を掲げながら「千人回峰」に臨み、千通りの「人とはなんぞや」がみえたとき、「人ありて我あり」の「人」が私のなかでさらに昇華されるのではないか、と考えています。
「千人回峰」というタイトルは、比叡山の峰々を千日かけて駆け巡り、悟りを開く天台宗の荒行「千日回峰」から拝借したものです。千人の方々とお会いして、その哲学・行動の深淵に触れたいと願い、この連載を続けています。
「人ありて我あり」は、私の座右の銘です。人は夢と希望がある限り、前に進むことができると考えています。中学生の頃から私を捕らえて放さないテーマ「人とはなんぞや」を掲げながら「千人回峰」に臨み、千通りの「人とはなんぞや」がみえたとき、「人ありて我あり」の「人」が私のなかでさらに昇華されるのではないか、と考えています。
株式会社BCN 会長 奥田喜久男
<1000分の第168回(下)>
※編注:文中に登場する企業名は敬称を省略しました。
※編注:文中に登場する企業名は敬称を省略しました。
ターニングポイントとなったアドビとの提携
奥田 少し時代はさかのぼりますが、1987年のアドビ システムズ(アドビ)との提携も、モリサワの歴史のなかでは大きな経営判断ですね。森澤 モリサワのターニングポイントになった出来事です。私は1986年に入社したのですが、その新人時代に「アドビとビジネスをすることになるので、一度米国に行ってこい」といわれ、87年4月から4か月間アドビにお世話になりました。
奥田 そのときのお話を聞かせていただけますか。
森澤 DTP(パソコン上で組版ができるシステム)の登場で出版やデサインの世界がどう変化するかをリサーチし、アドビという若いベンチャーの気風を学ぶために渡米しました。当時のアドビはサンフランシスコのパロアルト地区にあり、社員は全世界合わせても60人か70人くらいしかいませんでした。
奥田 そんなに小さかったのですか。
森澤 しかし、そのスタートアップともいえる時期に、アドビはすでにIBMと契約を交わしていたのです。当時、IBMが採用したものはデファクトスタンダードになるのがセオリーで、そこからアドビの快進撃が始まったといっていいかもしれません。4か月後に帰国する頃には、すでに社員は2倍以上の150人ほどになっていました。それくらい、急激にアドビが伸びていた時代ですね。
奥田 この提携は、経営的にどのような影響を与えましたか。
森澤 大きな影響を与えたことは間違いありません。ただ、その影響はモリサワにとって複雑なものでした。
奥田 具体的にはどのようなことですか。
森澤 当時のモリサワは、まだ手動写植機や電算写植機という自社開発したハードウェアの製造販売をメインビジネスにしていました。ところがDTPの登場によって、DTP向けのフォントをどんどん増やしていかざるを得なくなる。あたりまえのことですが、それが自社のハードウェアのビジネスを崩壊させていったのです。
奥田 印刷や組版技術の進化によって、変化を余儀なくされるということですね。
森澤 モリサワのハードウェアメーカーとしてのビジネスを終わらせたのはアドビであり、モリサワのソフトウェアビジネスの成長を支えてくれたのもアドビであるといえます。
「温故知新」とベンチャースピリッツ
奥田 最近の新しい試みにはどんなものがありますか。森澤 電子書籍の制作支援システムのほか、カタポケ(カタログ・ポケット)というインバウンド向けの自動翻訳サービスつきの電子配信ビジネスも行っています。
奥田 それはどんなサービスですか。
森澤 DTPソフトのインデザインやPDFなど、印刷用のさまざまなデータを、私たちが用意したオーサリングソフトを使って他の言語に翻訳したり、読み上げたり、検索することを可能にしたものです。例えば、日本語で書かれた観光案内や地域のフリーペーパーなどの情報を、多言語で見たり聞いたりすることができます。長期的には今後も外国人観光客の増加が見込まれ、2020年の東京五輪を見据えて、昨年からこのサービスを始めました。
奥田 これから期待される事業ということですね。それから、今年6月にさくらインターネットとの協業を発表されました。
森澤 当社のwebフォントサービス「TypeSquare」から30書体を「さくらのレンタルサーバ」利用者に追加料金なしで提供するというものです。
奥田 そのサービスにはどんなメリットがあるのですか。
森澤 ウェブサイトのデザインでは、モリサワ書体でも他社の書体でも、いままではフォントを画像化して貼っていました。その一番わかりやすい例がバナーです。ところがサイトをみるデバイスは多様であり、パソコンよりもスマートフォンのほうがネットにアクセスする機会が多く、そのスマートフォンも画面のサイズはいろいろ。そうするとウェブデザイナーはそれに合わせて画像化する文字の大きさやレイアウトをつくりかえる必要があります。ところがTypeSquareでは、クラウドにモリサワのフォントサーバーを置いておき、ユーザーがモリサワの書体を指定することで、モリサワフォントが入っていないデバイスにも表示に必要な文字の分だけアウトラインフォントを送り込みます。
奥田 文字を画像化しないで表示できるということでしょうか。
森澤 そうです。これによって制作コストも下がるし、ビジュアル的にもきれいになります。
奥田 ところで、写植・フォントの業界で、どうしてモリサワだけが一貫して時代をキャッチアップできたのだと思われますか。
森澤 創業者がベンチャーとして世界初の手動写植機をつくったわけですが、その息子たちの第二世代、そして第三世代の私たちは、ずっとその薫陶を受けてきました。祖父が亡くなったのが2000年、私が37歳のときですから、一緒にものを考えたり教えを受けたりする時間が十分にあったのです。少なくとも私たちの世代まではそうした創業者の志を守り、ベンチャースピリッツをもち続けていることができた。それが一番の理由だと思います。
奥田 森澤さんにとって、ベンチャーの定義は?
森澤 世の中にないものを次々につくり出すことですね。
奥田 実に明快ですね。片や職人技のデザイナーが書体の開発をコツコツと行い、片やクラウドサービスとのコラボレーションでフォントを配信する。古いものづくりの伝統を大切にすることと新しい市場に新しい発想で挑んでいくことが共存していますね。
森澤 私の好きな言葉が、まさに「温故知新」なんです。同じ事業ドメインで知識を蓄積してきたからこそ、環境の変化にも対応できるのだと考えています。
ですから、これまでお世話になった出版や印刷産業に対しては新しい価値を提供することと、新しいお客様である映像やIT、インターネット産業に対してすぐれたサービスを提供していく。それを繰り返しやっていくことが、私たちに求められているのだと思います。
こぼれ話
時代を読む力を備えるにはどのような訓練をしたらよいのだろう。人の話を聞く、読書をする。真理を追求するために集中力を鍛えて、歴史書を紐解く。会社のこともさることながら、我が人生の行く末も気になる。できることなら幸せに過ごしたい。この幸せというのも人の価値観によってさまざまだ。森澤さんはモリサワの創業家出の社長である。いわゆる御曹司だ。大阪本社にあるモリサワの歴史展示をみた。人と文字の歴史へのこだわりが伝わってくる。創業からおよそ100年の間に買い集めてきたものだ。学術的価値と資産価値の高い資料があたりまえのように置いてある。目を見張ってしまう。グーテンベルグの初版本には驚いた。森澤さんの好きな言葉は「温故知新」だという。時代を読む力を大切にしておられると思った。
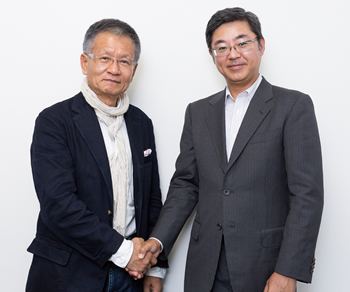
話を聞き進めるうちに気づいた。モリサワは、100年の間に築いた事業資産を打ち壊すような真逆の事業を手がけて生まれ変わっている。この力は遺伝子なのか風土なのか家訓なのか。「温故知新」という言葉に置き換えるとあまりにも通俗的な印象が強くなる。事業転換の時の経営決断は重い。創業家だからできるリスクを負える企業体といえよう。その一方でかつての強い相手はググってもサイトがみつからない。経営判断の行く末がここにある。






