“期待を裏切るような広告”は多くの人の感覚を揺さぶる――第282回(下)

後 貴芳美
そごう・西武 広告・宣伝担当
構成・文/高谷治美
撮影/長谷川博一
2021.4.9/そごう・西武本社応接室にて
週刊BCN 2021年5月24日付 vol.1875掲載
【東京・麹町発】生活者の嗜好やニーズが細分化され、コロナ禍がその流れに拍車をかける今、百貨店は窮地に立たされている。そごう・西武の年頭のCI広告「百貨店が売っていたのは、希望でした」はビジネスやマーケティングだけのためではなく、企業の想いをお客様へ、従業員へ伝える手段になった。SNSなどネットの反響が如実に出る分、「広告で売り上げが上がるのか」という厳しい意見もある。広告・宣伝担当の後さんはセゾンカルチャーに影響を受けてきただけに「売っているのは『モノ』だけではなく『文化(カルチャー)』なのだ」というルーツを大切にしてこられた。それはそごう・西武が掲げる『わたしは、私。』という、自分のスタイルをもつことへの強い情熱でもあった。
(本紙主幹 奥田喜久男)

子どもの頃から西武っ子
セゾンカルチャーは刷り込まれている
奥田 西武に入社されて20年ですね。西武に入りたいと思ったのは何歳ぐらいからですか?後 意識したのは就活の時です。子どもの頃から西武百貨店が身近で、もともと、池袋近辺に住んでいましたから学校から帰ってきて塾に行くのにも、池袋の西武百貨店地下でご飯食べてから行ったり。初めて洋服や化粧品を買ったのも池袋の西武百貨店でした。
奥田 なるほど、西武っ子だったのですね。
後 とにかくおもしろそうな会社だと思いました。シャッターに大きな絵が描かれてたりして、その存在感は衝撃的でした。学生の頃は店内に美術館もあり、現代アートやインテリアなどキラキラしたものが好きで、ちょくちょく観に行ってました。セゾンカルチャーが刷り込まれていたかもしれません。
奥田 西武がグワ~ッと伸びてる頃、華麗な時代ね。
後 糸井重里氏がつくった広告コピー「おいしい生活。」は、セゾンカルチャー全盛期の代名詞になっていました。「モノを売るより、カルチャーを売れ」というのがセゾングループ全体の方向性としてありました。百貨店も、カルチャーを売る場所みたいなことを大きく打ち出しながら、そこでモノを売って人の暮らしを豊かにしていこう、みたいな感じでした。
そんなルーツが今も流れているんではないかなと思います。
奥田 そのカルチャーには経営陣は入っていない?
後 今の経営層もセゾンのカルチャーに影響を受けてきた人たちでそのマインドを大切にしています。
奥田 そんななかで、後さんはお好きなアートやインテリアによって空間を演出することができて良かったですね。実は表現したい人だったのでしょう。
後 そうかもしれません。でも、自分が広告を生み出したり自分が携わったりするとは思ってもいませんでした。
奥田 どんなお子さんだったのですか?
後 父がフリーランスのフォトグラファーだったので、幼い頃にVOGUEや女性誌の撮影を観て楽しんでいる子でした。美術館に連れて行ってもらったりして、アートに触れる環境もありました。
奥田 大学時代はどんな経験をされましたか?
後 国際交流学部だったので、交換留学ができて、私は中国を選んで清華大学に行きました。
奥田 清華大学は理系で優秀な学校です。文系にも留学生がいたのですね。キラキラ好きなのにアメリカやヨーロッパを選ばなかったのはなぜでしょうか。
後 そうですね。そこでは自分が出せないと思ったのかもしれません。みんなが手を出していないマイノリティな領域を極めた方が楽しめるのではないかと、ずるいんですけど、そう思っていたところがありましたし、「なんで中国?」といった意外性を人に与えたかったというのもあります。
留学するまでは決まった友人としかつき合わないような閉鎖的なところもありましたが、中国へ行って変わりました。さまざまな人とコミュニケーションを取ることで、イメージで物事を判断しないほうが良いとわかったのです。世の中には、イメージとはまったく違う答えがあるということ。今の仕事のヒントにもなっています。
奥田 この頃から感受性の中で表現したいということへの刺激があったのでしょう。さて、表現するといっても、ネット時代なので広告の反響もさまざまだと聞いています。
売上高という指標が
すべてではなく体験や発見でお客様を元気にする
後 ネットの世界が進んでいくと、いわゆるコンバージョンレート(サイトの訪問者に対してどのくらいの人数が販売成果に結びついたかの割合を数値化したもの)での判断が主流になってきました。もっとも、ネットの世界が主流になってきていますが、私たち百貨店のようなアナログの世界は、売っているのはモノだけでなくてサービスだったり、私が幼少期に得たような体験・経験もありますから、売上高という指標がすべてではないと思っています。
奥田 そうなのですか?
後 そうですね。たとえば、ネットのECサイトだと、モノを買うとか具体的なアクションがお金に替わり、アクションを通じてコミュニケーションを取ってというようなところがあります。
ですが、店頭だと、お客様の気持ちが前向きになったりだとか、百貨店のいろいろなものを観て、新しい発見が出来たとか、モノを売る以外の場所という意味があります。本当は、うちに来てくださるお客様の気持ちをもっと温かくして差し上げることこそが大事なのではないのかということに、いろいろな反響があったおかげで、気がついたのです。
奥田 どんな反響?
後 2017、18、19、20年と企業メッセージである『わたしは、私。』を掲げて「私らしく生きる」にフォーカスして広告を打ってきました。17年『年齢を脱ぐ、冒険を着る。』、18年『正解はない。「私」があるだけ。』までは「いい広告だね」というコメントが多かったのに、19年の『女の時代なんていらない?』でジェンダー論がファクターになったり、20年の『さ、ひっくり返そう。』がテーマになると「これで何が売れるの?」「百貨店がやるべきことだったの?」というご意見もいただきました。
奥田 社内で?
後 いえ、SNSなのですが。広告が話題になればなるほど、世の中の反響がそういう議論にもなっていきました。私たちは、どちらかというと、モノを売るというよりは、百貨店にいらっしゃるお客様に、「あなたらしく生きてくださいね、そのお手伝いをわれわれはさせていただきます。」というメッセージをお届けしたかったのです。
奥田 20年の力士の「さ、ひっくり返そう。」ですね。これも後さんが担当されましたよね。一見、通常のメッセージ広告だし、ちょっとネガティブな印象ですが、下から読み返せばポジティブストーリーに逆転していきます。後さん、「いい意味でショックを与えたい」と言っておられましたが、こういうことですね。
後 そうですね。実は、この広告を作っている最中、西武岡崎店やそごう徳島店など5店舗の閉鎖が決まったので、お客様や社内的にも「逆境を乗り越えよう」といった強いメッセージが隠されてはいたのです。
奥田 しかし、世間は議論するのですね。「これで何が売れるの?」と。大きなお世話ですよね(笑)。
でも、百貨店って、もしかしたら、一人ひとりが自分のモノのように思っているのかしら?
後 そうですね、自分らしさをみつけてくれる場所、みたいに思われているかもしれません。
奥田 「わたしの西武」みたいな。同化しているのかもしれませんね。
後 ビジュアルでも、クリエイティブでも、考えて工夫を凝らせば、まだまだ人の心を動かすことができると信じています。
つい、目先の利益を優先し、宣伝活動に必死になってしまいますが、「人々の心を本当に動かし、豊かにする」のは目先の利益を追うだけではいけないということを表していきたいです。
サステナブル(持続可能)なテーマなど、表現することはいろいろあります。
奥田 来年の年頭の広告が楽しみですね。
こぼれ話
後さんとの対談の数日前、「子どもの体調が不安定なので」という理由で、予定日キャンセルの可能性が生じた。この連絡をもらって、社会活動は“生モノ”なんだと感じた。今さらながら、自分たちは生きているのだ、と思った。あの日も、そうだ。西武百貨店のある池袋駅東口を早朝に歩いた。コロナ禍もあって人通りは少ない。横断歩道を渡りながら信号機のシグナルを確認した。目に入ったのはその先の大きなショーウィンドウの文字だ。「百貨店が売っていたのは、希望でした」と……。何だろう、これは。何を言っているのだろうか。誰に対してのメッセージなのか。目が釘付けになった。そのディスプレイはとても大きなレシートだった。西武百貨店が2020年のある期間に販売した商品の数量のようだ。その領収書には、スーツケース、口紅、浴衣、ハイヒール、ベビーギフトの販売数量が印字されている。口紅は76,175本とある。この数値の根拠は何だろう。この数量は例年に比べて多いのか。コロナ禍であっても、予想以上に多かったのか。ベビーギフトとあるが、なぜベビーギフトを選んだのだろうか。数枚の写真を撮りながら、このコピーを考えた人に会いたいと思った。
“希望”という文字が私の心に刺さった。外出できない。人に会えない。世界中の人が監禁状態にある今、あらゆる人々が“希望”を求めている。いや、希望を持たないと、生きるバランスが保てない状態にある。だから希望という文字に引かれたのだ。「希望」は素晴らしい力を持つ言葉だ。実はそれだけではない。コロナ以前から明日をもがいている百貨店自身が希望を売っていたのだ、という自身のメッセージ発信に感動したのだ。
コロナ禍で人の動きが制約され始めて、所得の分配バランスが激変した。人に替わって機能を代行する仕事と、ビット化できる情報を操る大きな意味でデジタル環境にある業種業態は未来が明るい。もう少し冷静に社会の変化を追ってみよう。文明レベルの技術は社会構造の破壊と創造を繰り返してきた。グーテンベルグの印刷機は宗教改革につながった。インターネットの環境整備は印刷機と同様に文明レベルの変化を招く。
“三密”を避ける行動様式は、コロナ禍での行動様式とともに、ネット社会そのものからのメッセージではないか。三密回避を機会に社会構造の進化を求められているのではないか。音楽会、演劇、ライブコンサート、集会のあり方の変化。さらに在宅勤務の継続による家族との生活様式の変化。小さな変化は大きな構造変化につながる。明日はどうなるのだろうか。
まずは生モノである自分自身の“生き方”あるいは“なりわい”を見つめ直そう。「百貨店が売っていたのは、希望でした」を見た時、強く心が揺れた。後さんとの取材を進めながら、このキャッチコピーを考案したチームも希望を求めているのだ、と思った。
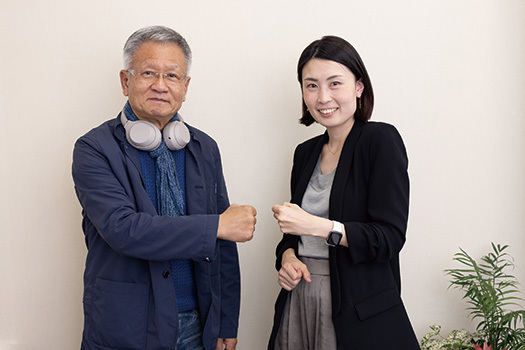
心に響く人生の匠たち
「千人回峰」というタイトルは、比叡山の峰々を千日かけて駆け巡り、悟りを開く天台宗の荒行「千日回峰」から拝借したものです。千人の方々とお会いして、その哲学・行動の深淵に触れたいと願い、この連載を続けています。
「人ありて我あり」は、私の座右の銘です。人は夢と希望がある限り、前に進むことができると考えています。中学生の頃から私を捕らえて放さないテーマ「人とはなんぞや」を掲げながら「千人回峰」に臨み、千通りの「人とはなんぞや」がみえたとき、「人ありて我あり」の「人」が私のなかでさらに昇華されるのではないか、と考えています。
※編注:文中に登場する企業名は敬称を省略しました。
Profile
後 貴芳美
(うしろ きほみ)
1979年、東京生まれ。池袋で育ち、西武百貨店は身近な存在だった。1998年、大学在学中に中国の清華大学に交換留学し、グローバルな視野で物事を考えるという貴重な経験をした。2001年、西武百貨店に入社。2008年より販売促進部に所属し、商品部を経て装飾担当として2018年までディスプレイプランニングのキャリアを積む。手がけたディスプレイは、「30日間アドベントカレンダーのように変化を続けるショーウインドウで2017年DSA日本空間デザイン金賞を獲得」など多数。催事プロモーションのディレクションも行う。2019年より広告宣伝担当に移り、年頭のCI広告2020年の「力士の炎鵬」、2021年の「レシート」の広告では中心的に関わる。一児の母でもある。






